大学生向け『退職代行業者が伝えるブラック企業の見分け方』のテーマで講師として登壇(谷本慎二)

代表の谷本が、国立大学労働法ゼミ主催の講演会に講師として登壇しました。
労働法ゼミの学生に向けて「退職代行業者が伝えるブラック企業の見分け方」をテーマに、累計約4万件にのぼる退職代行の事例データをもとに講演を行いました。
講演会やコンサルティングなどのご依頼は、MOMURI+(モームリプラス)の問い合わせフォームまたはLINEにて承っております。
公演実施の背景
この度、国立大学の教員の方より「ブラック企業、ブラックバイトの問題を挙げ活動している労働法ゼミというゼミがある。その学生に向け、講演会をしてほしい」とのご依頼を受けました。
過去には19回の講演を行い、今回で20回目の登壇となります。
過去のセミナー講演実績
- 看護師の離職対策カンファレンス(主催:アウトカムマネジメント株式会社)
- 退職防止講演(主催:東京都信用金庫協会)
- 人材流出防止セミナー(主催:彦根商工会議所)
- 新卒の離職率低下について(主催:大学職業指導研究会)
- 看護師等の離職防止・定着促進セミナー(主催:総合メディカル株式会社)
- 総院長ゆうきゆう先生と弊社代表の対談(主催:ゆうメンタルクリニック)
- コールセンター従事者(企業)向けセミナー(主催:株式会社リックテレコム)
- ブラック企業の見極め方(主催:私立大学)
- 医療従事者の人材定着率向上について(主催:総合メディカル株式会社)
- 製造業従事者の離職防止策(主催:株式会社パソナ)
- やめない会社をつくるために(主催:株式会社新潟日報社)
- 保育士の離職を減らすために(主催:社会福祉連携推進法人あたらしい保育イニシアチブ)
- Z世代が離職しない職場作り(株式会社リックテレコム、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社)
- 保育士の離職を減らすための方法(主催:一般社団法人長崎県保育協会)
- せっかく入ったスタッフが速攻で辞めちゃう理由(主催:ワンディー株式会社)
- 離職者の本音と離職防止策(主催:人材不足・人手不足 対策EXPO実行委員会)
- 情報に惑わされない!企業選びの確かな目を養う(主催:国公立大学)
- 退職代行業者から見た離職者の本音とZ世代の考え方(主催:一般財団法人 日本産業カウンセラー協会)
- 退職代行を使われない会社づくりの方法(主催:歯科クリニック)
講演の概要
退職代行業者が伝えるブラック企業の見分け方
依頼趣旨
労働法ゼミの学生から「近年注目されている退職代行サービスについて話を聞きたい」との要望があり、そのお声を受けてのご依頼です。累計約4万人の退職代行を確定させてきた経験をもとに、大学生のうちから知っておきたい「ブラック企業の見分け方」や、25年新卒の実際の退職データをもとに講義を実施。学生が社会で直面する課題を理解し、将来の働き方を考えるきっかけを提供することが目的としています。
講演詳細
開催日時:2025年6月24日 17:00~18:45
開催地:国立大学
参加者:大学3年生、4年生
参加人数:20名
講師:谷本慎二(株式会社アルバトロス代表取締役/退職代行モームリ代表)
主催:非公開
講演内容
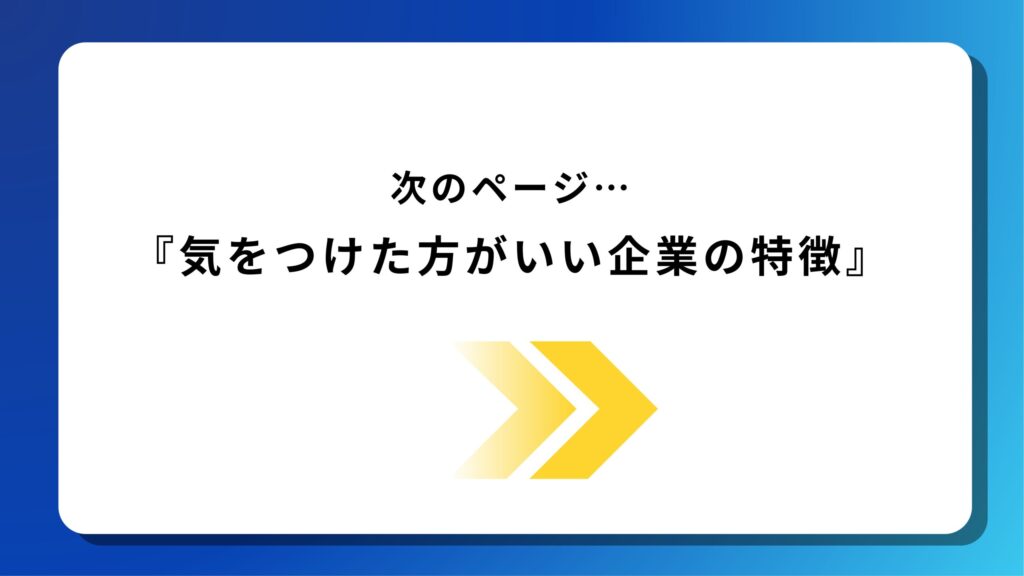
➀会社紹介/退職代行について
弊社代表の経歴に加え、提供しているサービスや事業全体の概要について紹介しました。
②25新卒社員の退職代行利用者データ
25年新卒社員の最新退職代行の利用者データを共有しました。退職理由とともに、雇用形態・業種のデータを開示し、全体として共通する退職理由を提示しました。
③企業選びのポイント
企業選びの前提となる基本的な考え方や、チェックしておきたいポイントについて解説しました。さらに、求人情報の中で特に注意して見るべき項目についても詳しく解説しました。
④気をつけた方がいい企業の特徴
退職代行業者の視点から『ブラック企業』と呼ばれる企業の特徴や、ブラック企業とまではいかないが、気を付けた方がいい会社の特徴を解説しました。また、実際に寄せられた退職理由もお伝えしました。
⑤まとめ
企業を見極める方法やについて、簡潔にお伝えしました。
⑥質疑応答
講義後には、大学3年生の方や就活を終えた大学4年生の方から質問を受け、それぞれ回答しました。以下、当日あった質問内容を記載します。
質問内容(大学3年生より)
- 退職代行サービス自体はいつから?
- 他者との差別化は?
- 退職代行サービスを利用するべき人は?また、しないほうがいい人は?
- 利用される8割の20.30代は勤続年数は短いの?利用者の傾向を知りたい
- その中には長い方もいる?
- 依頼された企業の就業規則に退職代行禁止があった場合の対応は?
- どこまで退職の手続きを進めてくれる?
- 連絡時にうまくいかないスムーズにいかない場合もあるがどうするのか?
- 今後の転職に影響はあるか?
- 退職代行サービスで働いてる人のやりがいや達成感はある?
- 会社に置いてある私物に嫌がらせされたりしないのか?
質問内容(就活を終えた大学4年生より)
- モームリのような急成長された企業の課題は?
- 今後の事業展開は?
- セクハラや人格否定される退職代行利用者は、若い世代に多いイメージだが、中高年の世代の方が利用される理由は?
- 仕事を辞めることに向き合っていく中で働くことに対する谷本社長の意識の変化は?
- 退職代行サービスは、モームリができる前からあるが、業界トップなのはなぜ?透明性以外の理由もあるのか?
講演会を終えて
今回の講義には、大学3年生を中心に20名の学生が参加しました。就職活動を終えた4年生も出席し、パソコンでメモを取りながら熱心に耳を傾けている様子が印象的でした。
特に興味深かったのは、「社訓の唱和は“あり”か“なし”か」という問いかけに対して全員が「なし」と回答し、「退職代行はあり」と満場一致で手を挙げた場面です。
また、労働法を学んでいる学生であっても、「無期雇用の場合、退職の意思を伝えてから2週間で退職できる」といった基本的な知識を知らない方が多く、労働にまつわる講義の必要性を改めて実感しました。
講義を依頼してくださった大学教員の方からは、「他の大学にも紹介して広めていきたい」とのお声をいただきました。
実際に、すでに他大学や中学校からも講義のご依頼をいただいており、今後さらに需要が高まっていくことが予想されます。
このような講演や企業・学生向けのコンサルティングや相談会は、個別対応も可能です。


