仕事を続けていると誰しもが一度は「退職したい」という想いを持ったことがあるのではないでしょうか?
また、一大決心をして退職を伝えた際に「就業規則にあるように〇か月前までに退職の意思表示が必要」と言われ、退職を先延ばしにされたことがある方も少なくはないと思います。
ここでは、退職を考えた際に、実際には最短でいつ辞めることが出来るのかを法的観点からお伝えしていきます。
退職の意思を示してから2週間で退職は確定する
あまり知られていない事ですが、法律に以下の様にしっかりと明記されています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条一項
つまり、無期雇用(雇用の期間を定めない雇用契約)であれば、退職の意思を伝えて2週間で退職は確定します。
退職の意思はどのように伝えればいいか
その退職の意思というのは、書面でなくとも口頭やメールなどの文章でも効力があります。
そのためどのように伝えても退職は可能ですが、聞いた聞いていないの問答になることもあるため、書面で提出までしておくのがいいでしょう。
その場合は退職願ではなく、必ず『退職届』を提出するようにしましょう。
なぜそうなのかはこちらの記事でご紹介しています。
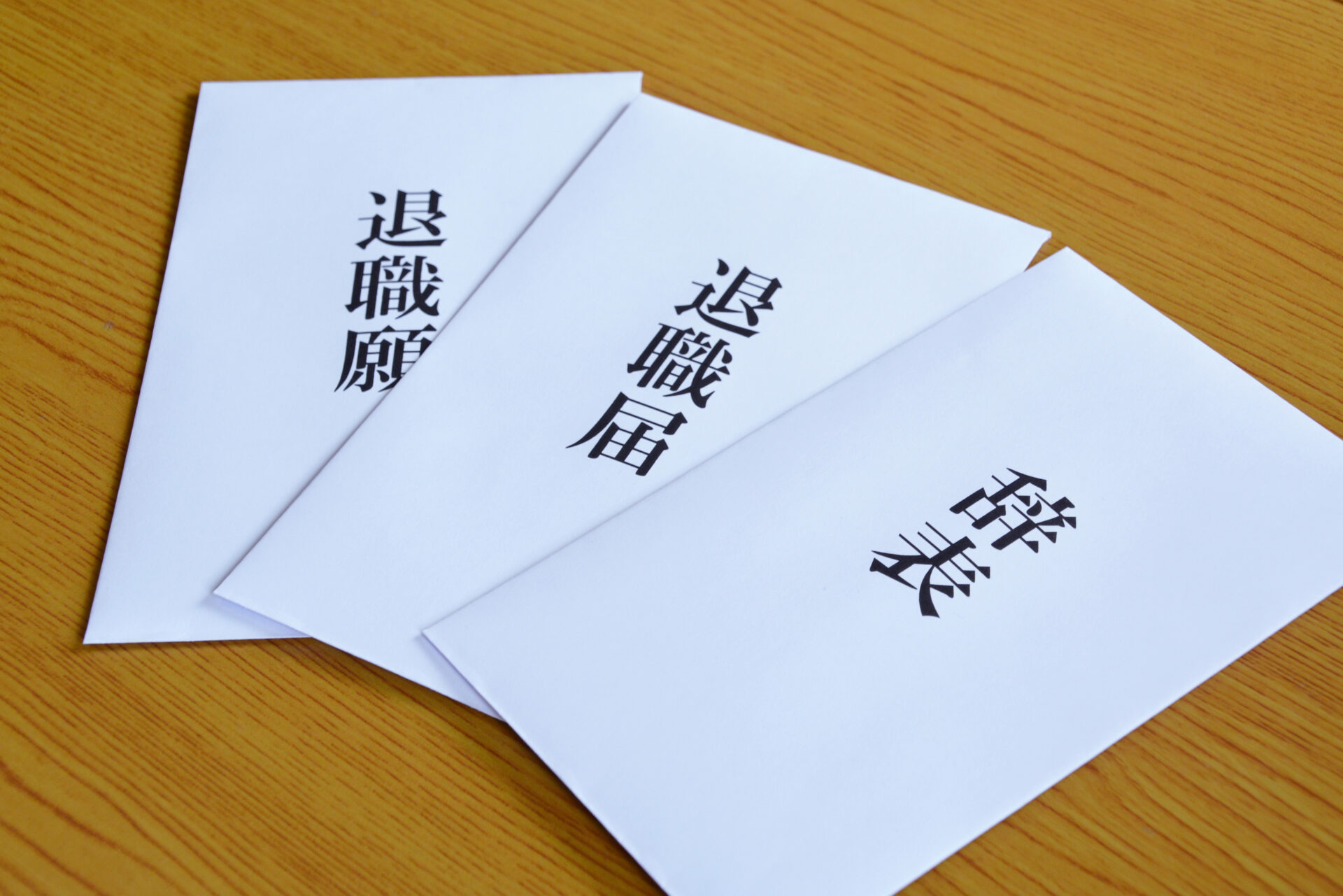
2週間は働かないといけないのか?
法律で2週間後に退職が確定すると書いてあるからといって退職日が必ずしも2週間後になるわけではありません。
『最長で2週間』と考えておくのが正しいです。
精神的・肉体的理由などの理由さえあれば、会社との交渉によっては最短即日の退職であったり、希望日の退職も可能となります。
また、それが難しい場合でも体調不良などの理由により、欠勤して2週間後の退職日を迎えることも可能です。
契約社員などの有期雇用の場合は?
契約社員に関しては正社員と違い『やむを得ない事由』が必要とはなりますが、それらは精神的・肉体的理由が該当します。
なので、
・パワハラを受けている
・病気を患っている
・事情により引っ越しが必要になった
・仕事がプライベートにまで影響する
・睡眠障害、食欲不振
・契約内容と実態が聞いていた内容とちがう
・身体的理由、精神的理由により仕事ができなくなった
・家族の介護がある
上記は一例ですが、こういった事例があれば『やむを得ない事由』に当てはまるため、即日の退職が可能となります。
有期雇用(契約社員などの期間の定めがある雇用形態)の場合は勤続1年を超えた場合は即時退職が可能ですが、退職には『やむを得ない事由』が必要となります。
有期雇用の退職に関しては以下の記事にて詳細に説明しています。
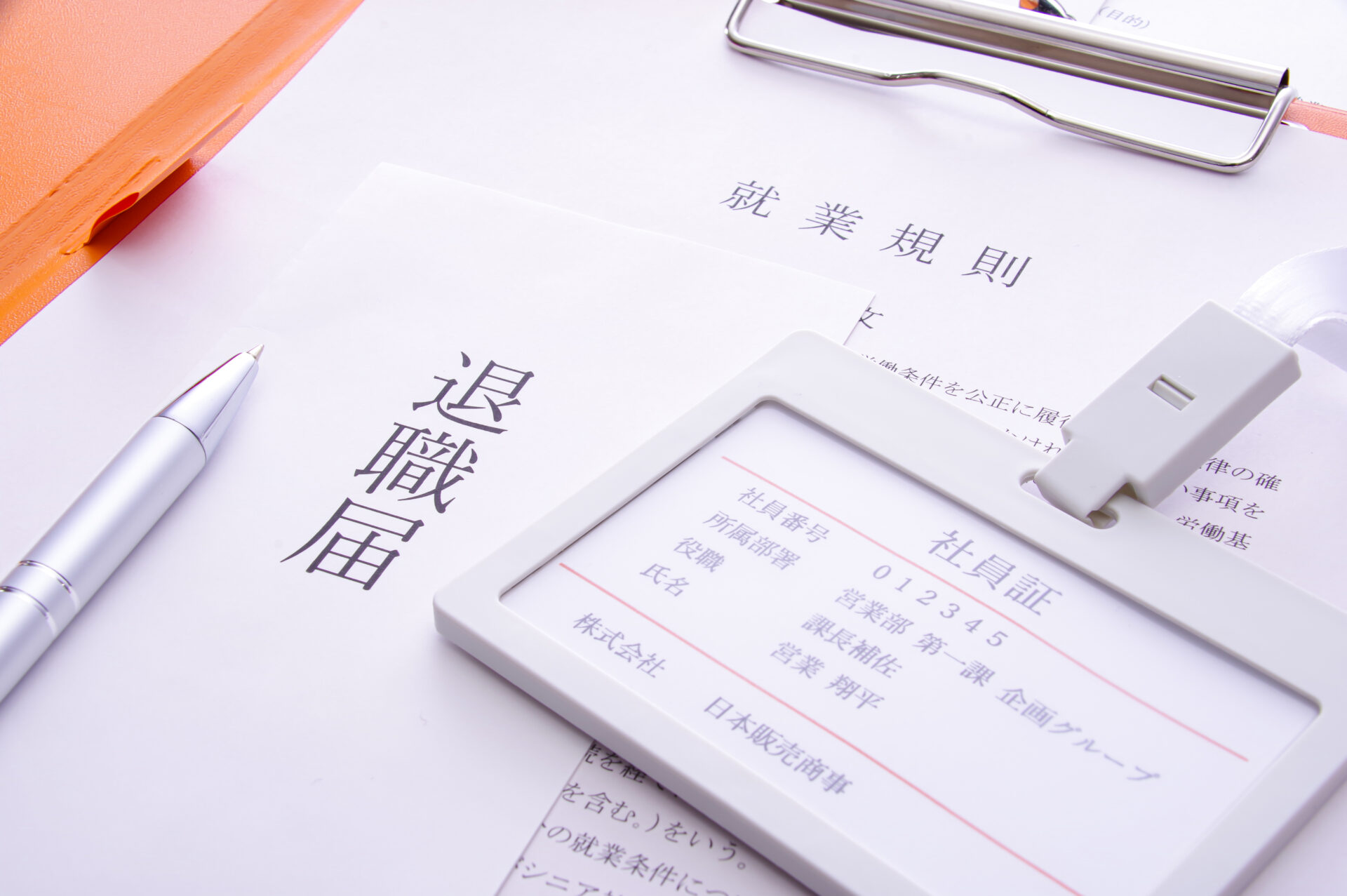
就業規則で〇か月前の退職意思の申し出が必要と記載してある場合
よく『会社の就業規則で1か月前に退職意思の申告が必要と書いてある』といった話を聞きます。
今まで聞いた中では、最長で「6か月前までに申告が必要」と書いてある会社もあると聞きました。
結論から申し上げると、
就業規則よりも法律が優先されるため、その就業規則の内容は無効。
つまり、法的にも最長2週間で退職は確定する。
この上記の内容がすべてとなります。
では就業規則の意味とは?
就業規則とは厚生労働省のHP内にも記載がありますが、
労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについ
て定めた職場における規則集です。
厚生労働省【リーフレットシリーズ労基法89条】
職場における規則集=社内ルールです。
職場でのルールを定めて、会社と労働者のお互いがそれを守ることで、労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要ではありますが、あくまで『社内ルール』というところが重要です。
社内ルールが法律に勝つことはできないので、退職は2週間で確定するという事になります。
総務知識を正しく理解して、無理のないワークスタイルを
この記事で記載してある知識があれば『退職できない』という事はあり得ませんが、世の中には以下の記事であるようなとんでもない会社は山ほどあります。

生きていくうえで仕事は絶対に切り離すことはできません。
就職・退職・転職、ほとんどの方が人生で一度以上経験することになります。
『無期雇用の場合、法的に退職は2週間で確定する。』
『有期雇用の場合は、やむを得ない理由で即日退職できる。』
この知識があるだけで、気持ち的にも楽になる方は多いのではないでしょうか。
そのためにもご自身の雇用形態は入社時に確認をすることが重要なので、しっかりと雇用契約書は確認し、いつでも確認できるように保管をしておきましょう。
しかし、会社に退職を申し出ても、なかなか退職することができないこともあります。
そのような場合は、確実に退職することができる以下のサービスを利用するのを検討してみるのも良いでしょう。

自分で退職、必ずできます。
~お世話になった会社、だから自分で退職したい~
自分では退職できそうにない、それでも退職代行には頼りたくない。そういった方にコンサルティングを行います。

口コミ満足度・人気NO.1退職代行
~もうムリだ!っと会社で感じたら~
退職代行モームリは『二名の顧問弁護士監修×充実した提携サービス×株式会社の管理』で、ご依頼後は出勤や会社と連絡をすることなく、確実に退職が可能です。











