
電話対応が苦手すぎる!どうにかしたい!



電話対応って難しいですよね。電話対応の克服方法について一緒に考えていきましょう!
電話恐怖症といった言葉があるほど、「電話対応が苦手で辛い」と考えている人が増加しています。
若年層はテキストメッセージやSNSといった非対面・非同期型のコミュニケーションに慣れており、「即座に返答が求められる」電話に対して強い緊張を抱きやすい傾向にあります。
引用:ライブドアニュースより引用
特に、20代の世代は友人と連絡を取り合う際は、インスタグラムやX(旧Twitter)などのSNSに搭載されているDM機能を使うと回答した人が8割越えです。(ソフトバンクニュース参照)
今回は電話対応が苦手な人の特徴、克服方法やおすすめアイテム、退職代行モームリの現場にて電話対応している社員にもインタビューを行いました。



実際に電話対応の克服された方の体験談も紹介しています。
電話対応が苦手な人の特徴
電話対応が苦手な人の特徴は4つです。
緊張しやすく繊細な性格
自他ともに認める超繊細さんなので、何気ない電話をしたときに塩対応されるとそのあと1日引きずる… きっと対応した方は何とも思ってないからこちらの受け取り方の問題なんだろうけど、もっと上手に生きられるようにないたいよね。
— ゆいゆい (@yuiyuiseikatsu) December 7, 2023
緊張しやすく繊細な性格の場合、電話対応が苦手と感じやすいです。
電話は対面のコミュニケーションとは違い、声だけでのやりとりとなります。コミュニケーションの難易度が上がり、繊細な性格の方だと、相手が意図していなくとも「威圧的・高圧的」に感じてしまう恐れがあります。



声が大きいだけでも、怒っていると感じる場合も…。
トラウマや失敗経験がある
電話対応の仕事してる人って尊敬するよね。
— エコル@トリシャ (@ekoru2222222) August 12, 2025
私なんか理不尽なクレームで怒鳴られる電話1回でもしばらく再起不能になるよ🫠
電話対応でのトラウマや失敗経験があると、電話対応に苦手意識が強くなります。例えば、電話越しで顧客から相談に誤って対応し、上司に叱責されるなどの体験です。理不尽なクレームや上司からの叱責を受けると、電話対応への苦手意識がより強くなります。
トラウマや失敗経験を糧にステップアップできる場合もありますが、「もう怖くて電話に出たくない!」と電話対応に拒否感が出てしまう場合もあります。
ビジネスマナーに自信がない
ビジネスマナーに自信がないと、会社での電話対応も自信がなくなります。
「会社に迷惑かけたらどうしよう…。」「失礼な対応をしてしまっていたかも…。」と会社での電話対応に不安でいっぱいになり、電話対応が苦痛に感じてしまいます。
ビジネスマナーとして敬語を身につけることで、電話への不安も減っていくと考えられます。
電話対応の重要なポイント


ビジネス敬語


ビジネスマナーを学ぶ一冊
電話経験が少ない
電話経験が少ないと、電話対応に苦手意識が強くなります。例えば、Z世代(1990年代後半から2010年代前半に生まれた世代)は家庭用電話機が自宅にない場合が多く、電話経験が少ない人も増えてきました。



昔と比べて、プライベートで電話をする機会が激減していますね。
電話を使う機会がないと、電話に対するハードルが上がるので苦手意識も上がります。言い換えると、電話をする経験を多く積むことで、電話への苦手意識が軽減できると言えます。
電話対応の克服方法
電話対応に慣れるためには、事前準備が大きなポイントとなります。具体的な対策は2つです。
マニュアルを作成する
電話対応マニュアルを作成して、事前に準備すると電話対応の苦手意識が薄れます。例えば、取引先・社内の人・業者など、パターンに合わせたマニュアルを作成し、社内で共有するのも有効です。事前にどのような電話がかかってくるかパターン別に把握しておくと、慌てずに対応できます。



新卒社員など、若い世代に対してはロープレなど研修に盛り込んでもいいですね!
会社のマニュアルがない場合は、電話対応の本などを参考に、自分なりのマニュアルを作るのも効果的です。自分なりに流れをまとめることで頭が整理され、落ち着いて対応できるようになります。
電話応対についてオススメ本
メモが取りやすい状態にする
いつでも電話対応ができるように、常にメモを取りやすい状態にしましょう。事前に環境を整えておくことで、焦らず対応できるようになります。
また、引継ぎミスなどが起こらないように【いつ・誰から・どのような案件】で電話がかかってきたかをメモすると取り次ぎもスムーズです。電話メモ付箋などのアイテムを有効活用して、聞き取りミスを減らし電話対応の苦手意識を軽減していきましょう。
電話付箋メモ
電話対応のプロに聞く!克服方法はナシ?!


電話対応を日々行っている、電話対応のプロに電話対応のコツや恐怖心の克服法などを伺いました。
日々、電話対応の業務をおこなう退職代行モームリの社員さんにインタビューをしました。
ズバリ!克服方法はありません。克服するより、自分が相手の反応に鈍くなるほうが、やりやすくなりますよ。正直最初は「この案件怖いなぁ…」など気にしますが、100件中の1件と割り切って淡々と業務します。
架電(自分からかける電話)したくない理由を探さないのがポイントです。受電(かかってきた電話)は「自分が全部取らなきゃ!」と気負いせず、慣れるまで1つ1つゆっくり行いましょう。
1件1件完璧に対応できなくても、『経験を積んで電話対応に慣れる』ことがコツです。
電話対応を克服した人へ聞いてみた
退職代行モームリでは退職の通知を会社に代わっておこないます。日々、電話対応の業務をおこなうモームリの社員3名にインタビューをしました。
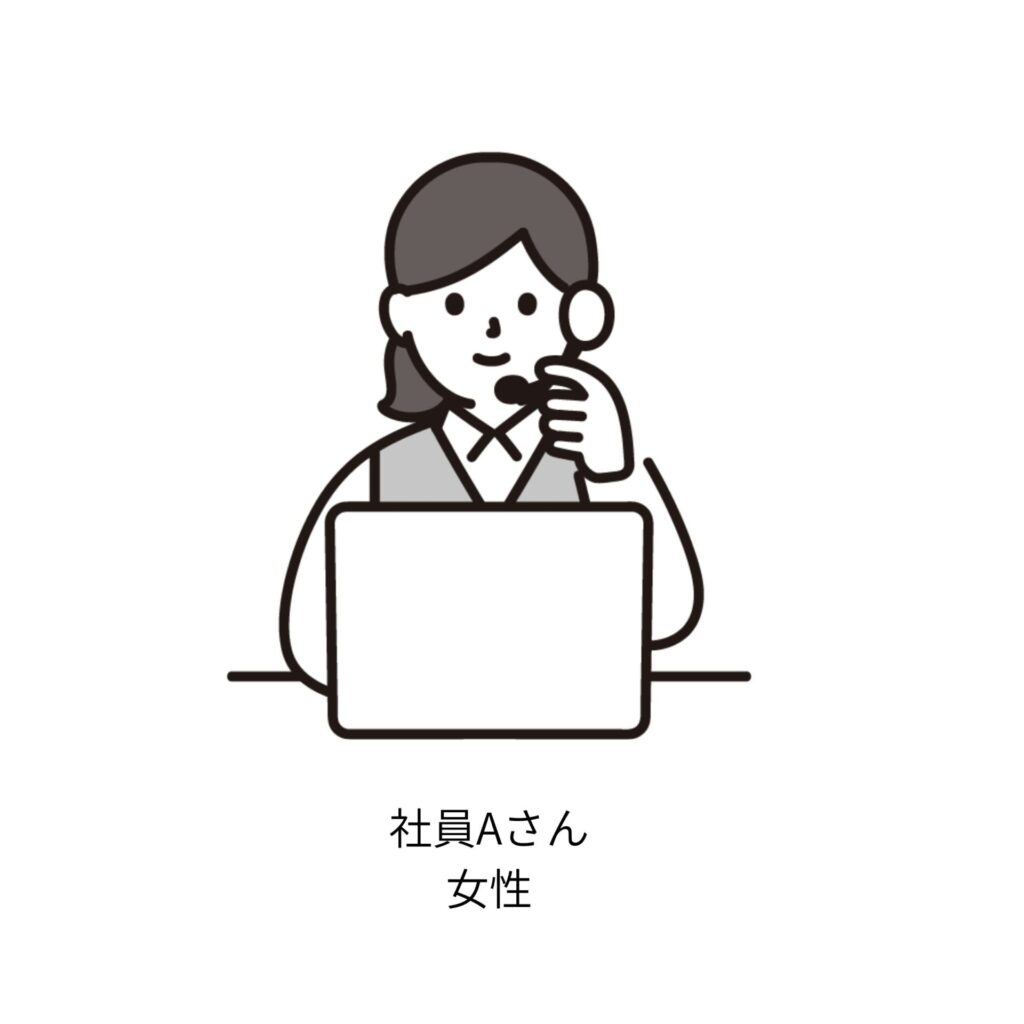
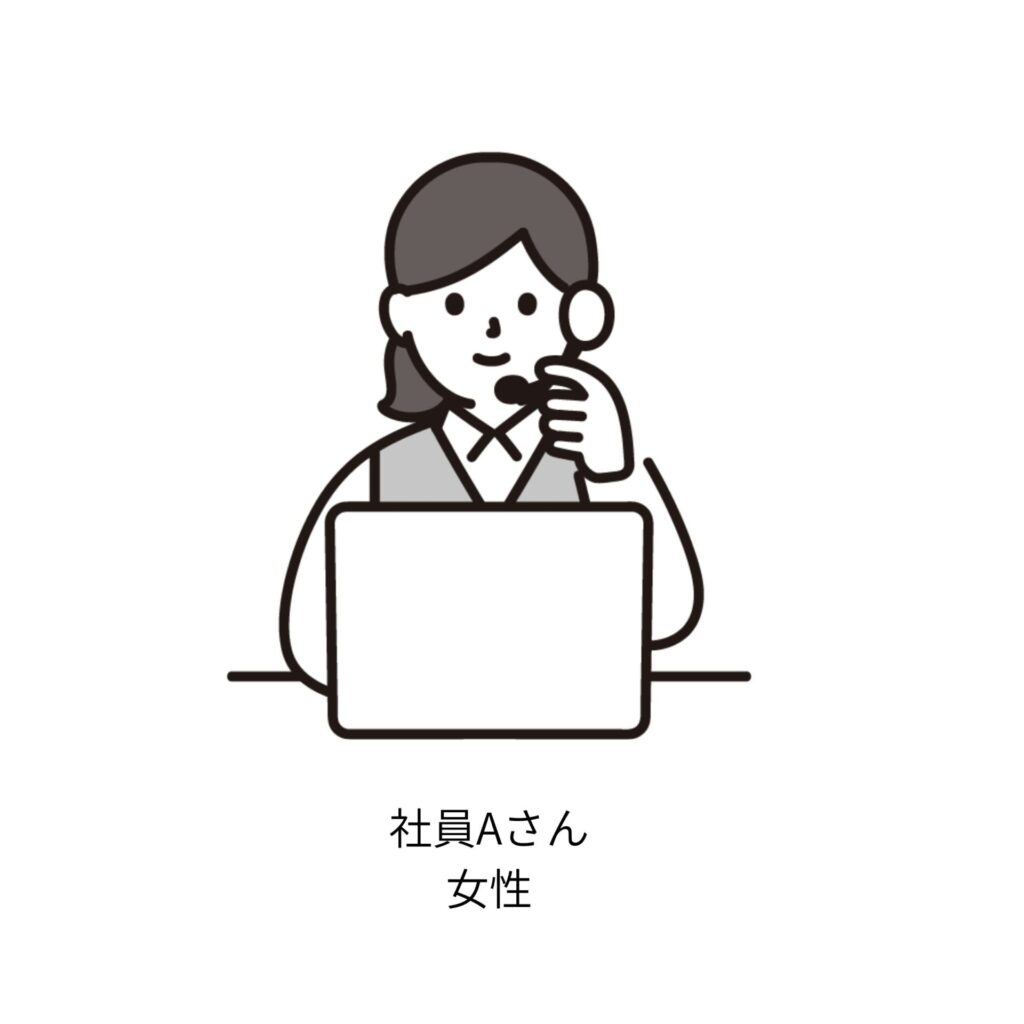
電話対応の経験はどのくらいですか?
1年ほどです。(社員Aさん)
電話対応の苦手意識をどうやって克服しましたか?
苦手意識は場数踏んで、克服しました。(社員Aさん)
電話対応が苦手で、内容が聞き取れません。工夫していることはありますか?
どうしても聞き取れなければ、メールに切り替えるのも1つの手です。(社員Aさん)
電話対応テンパってしまいます。どうすればいいですか?
ゆっくり話す意識を持ちましょう。ぬいぐるみやリラックスボールなど癒しのアイテムを導入したらどうでしょう!(社員Aさん)
電話対応が苦手なので辞めたいです。電話対応をしない人をどう思いますか?
苦手であるのは仕方ないです。会社に電話対応の少ない仕事の転換をお願いしましょう。(社員Aさん)
- 電話対応の経験はどのくらいですか?
-
電話対応を始めて半年です。(社員Bさん)
- 電話対応の苦手意識をどうやって克服しましたか?
-
前職で電話対応がほとんどなかったので、最初は緊張していました。「伝える内容」と「自分にできる事」は決まっています。会話ではなく「情報の通知」と意識すると気持ち的に楽になるのでおすすめです。ただ、相手には冷たく機械的と感じてしまうかもしれないので、バランスが必要ですが…!(社員Bさん)
- 電話対応が苦手で、内容が聞き取れません。工夫していることはありますか?
-
誤った情報でトラブルになるより断然良いと考え、少しでもわからない内容があれば、聞き返します。基本的には相手も優しく、言い直したり、かみ砕いて説明してくれます。暴言を吐かれるなどで話が進まない場合は、電話以外のツール(書面やメール)などで対応すれば大丈夫です。ただし、これは会社の方針にもよるので、対応に困ったら上司に指示を仰ぎ対処すると良いと思います。(社員Bさん)
- 電話対応テンパってしまいます。どうすればいいですか?
-
間違えても、普通は優しく言い直したり間を取ってくれます。もし、相手が高圧的な対応でしたら、「情報の通知」を徹底し、会話の主導権を握るように意識するとよいです。(社員Bさん)
- 電話対応が苦手なので辞めたいです。電話対応をしない人をどう思いますか?
-
得意な業務を伸ばしていけばいいので、電話対応をしたくない場合は、しなくてもいいと思います。逆に電話対応が得意な人もいるかと思いますので、得意な業務をすればよいと思います。(社員Bさん)




- 電話対応の経験はどのくらいですか?
-
4年半ほどです。(社員Cさん)
- 電話対応の苦手意識をどうやって克服しましたか?
-
自分から積極的に電話に出ることで、電話対応に慣れるよう努力しました。(社員Cさん)
- 電話対応が苦手で、内容が聞き取れません。工夫していることはありますか?
-
自分から聞く姿勢を整えて、ゆっくり話すようにしています。(社員Cさん)
- 電話対応テンパってしまいます。どうすればいいですか?
-
聞く姿勢を整えて、ゆっくり話すようにしています。(社員Cさん)
- 電話対応が苦手なので辞めたいです。電話対応をしない人をどう思いますか?
-
苦手なのは仕方がないので、まずは周りの人と色んなパターンで練習してみるのも1つかと思います。(社員Cさん)
以上、退職代行モームリの電話対応業務を行っている社員さんのインタビューです。実際に、電話をどのように対応しているかは、退職代行モームリのYouTubeチャンネルにて紹介しています。
電話対応克服するためのおすすめアイテムとサービス
電話対応の克服を手助けしてくれる、おすすめアイテムとサービスを紹介します。
高性能ヘッドフォン:JBL QUANTUM 100M2 ゲーミングヘッドセット
電話対応の際、うまく聞き取れず苦労する場合があります。聞き取りやすいヘッドフォンタイプのヘッドセットで、聞き漏れもない環境を整えましょう!
JBL QUANTUM 100M2 は、ヘッドフォンが軽量で長時間の使用でも疲れないのでおすすめです。
Amazonで購入可能
電話対応のない職種へ転職:アルバトロス転職
電話対応でトラウマや失敗経験で心に深い傷を負ってしまい、会社に行くのが辛い場合は電話対応のない環境への転職も視野に入れましょう。例えばコールセンターや事務職から、ITエンジニア職に転職すると電話対応の機会が減ります。
アルバトロス転職は全国・全職種15万件以上の求人情報を保有しているので、電話対応が少ない仕事への転職が可能です。


アルバトロス転職なら、常時15万件以上の求人を保有。相談から内定まで全てLINEで解決することができます!年中無休365日9時~21時で受付をしており、履歴書作成のサポートや面接対策も実施しています。
\履歴書内容も細かく伝授!/
アルバトロス転職のリアルな口コミや評判は、以下の記事で確認できます。


電話対応が苦手でも克服できる!


電話対応が苦手な人の特徴から、電話対応が苦手だったが克服した方の経験談を紹介しました。
電話対応を苦手とする人は多くいます。1人で悩まず、経験を積んでいけばスキルアップに繋がります。



どうしても電話対応が苦痛な場合は、配置転換や転職を視野に入れるのも1つの手です。
マニュアルを作る、メモを取るなど対策をして、電話対応への不安を減らしていきましょう。











