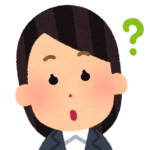
「副業はメリットが多い」って言われるけど本当?



副業には多くのメリットがあります。働く人だけでなく企業側にもメリットがあります。
令和に入り、働き方改革や人手不足を背景に、副業を解禁・推奨する企業が増加している現状があります。また、コロナ禍以降のリモートワーク拡大で副業がより身近になりました(※厚生労働省|副業現状について参照)。
今回は労働者と企業、両者の視点で副業のメリット・デメリット・税金面をわかりやすく解説します。
【労働者側】副業するメリット


副業を始めることで得られるメリットは数多くあります。
働く側が感じる代表的なメリットを4つ紹介します。
収入アップと経済的安定
副業の最大の魅力は、収入アップです。物価上昇や将来の不安が高まる中で、収入源が一つ増えるだけでも心の安定につながります。



物価高で将来不安の中、収入源を増やせると安心ですよね。
たとえば、月3万円の副収入があるだけでも、年間36万円の余裕が生まれます。36万円を貯金・投資・スキルアップ費用などに自由に使え、副業前より豊かな生活を送れます。
また、収入の柱を増やすことで、万が一本業の収入が減少してもリスクを分散できるのも大きなメリットです。
スキルアップ・キャリア形成
副業を通じて、新しいスキルを身につけられるのも大きなメリットです。たとえば、事務職の方がWebライティングを始めると、文章構成力や情報発信力が向上し、本業の資料作成や企画書作成にも好影響を与えます。
また、副業で培った経験が将来的な転職・独立の準備にもつながるケースもあります。
「自分にはどんなスキルがあるのか」「市場でどれだけの価値があるのか」を知る機会ができ、キャリア形成の視野を広げるきっかけにもなります。
人脈拡大と新しい価値観との出会い
副業を通じて、本業では出会えないフリーランスや異業種の人との交流から、新しい出会いや価値観を得られる場合もあります。
本業以外での出会いは、仕事だけでなく人生の視野を広げるきっかけにもなります。「副業をきっかけに起業した」「副業を行って稼ぐ難しさを痛感し、本業をより頑張れるようになった」といった人もいます。
精神的な充実感
副業を行うと、「自分で0から稼げた」と自信がついて、精神的な充実感を得られます。



自分で1円でも稼ぐと、何よりも大きな自信になりますよね。
また趣味や特技を活かした副業を行うと、仕事に対するストレスを軽減できるケースも多いです。例えば、趣味の手芸やイラストを「メルカリ」や「minne」で販売して収益をえるなど、趣味の延長で行えると精神的な充足感も高まります。
【労働者側】副業デメリットと注意点
労働者側の副業のデメリットと注意点は以下のとおりです。
時間・体力の負担
副業を始めると、自由に使える時間が減ります。副業に時間をかけすぎて、本業に支障が出るリスクを頭に入れ、余裕あるスケジュールで副業を無理なく続けるのが大切です。



私も過去に副業した経験がありますが、納品の締め切りが迫っていて夜中の3時頃まで作業したこともありました…。自分のキャパを理解してスケジュールを組むよう心がけましょう。
特に本業が忙しい時期には、睡眠不足や体調不良を招いてしまいます。1日1時間からなど、無理のないスケジュール管理で余裕を持って始めるのが成功のコツです。
税金・確定申告の手間
副業を始めると避けて通れないのが税金問題です。
副業が良しとされていない環境の人は住民税の金額から会社に副業が知られてしまうケースもあります。
確定申告時には「普通徴収(自分で納付)」を選択するなど、事前の対策が重要です。
確定申告書の住民税に関する項目で、「普通徴収(自分で納付)」を選択します。
「普通徴収(自分で納付)」を選択すると、副業分の住民税の納付書が自宅に届くため、本業の会社に副業の所得情報が知られることを防げます。
本業の会社から渡される年末調整の書類には、副業の所得を記入する必要はありません。年末調整の後に自分で確定申告を行うことで、正確な所得を申告できます。
企業の就業規則・副業禁止ルールを確認
副業を行う前に、勤めている会社の就業規則を必ず確認しましょう。
会社によっては「事前申請が必要」「競合他社での副業は禁止」など、明確なルールが定められています。
また、公務員は法律で副業が制限されている点にも注意が必要です。
トラブルを避けるためにも、情報漏洩や利益相反のリスクに注意し、きちんと確認をとった上で副業を行いましょう。
地方公務員の副業は、2025年6月から緩和の傾向にあります。
地域や職種によって状況は異なりますが、社会貢献を目的とする副業については認められるケースが増えています。
今後は、公務員もより副業しやすい環境になっていくかもしれません。
【企業側】副業メリット
企業側にも従業員が副業するメリットがあります。企業側が受けるメリットは以下の3点です。
社員のスキルアップとモチベーション向上
副業で得たスキルや知識は、本業にも還元されます。例えば、社員が副業でWebマーケティングを学べば、会社の広報や営業にも役立ちます。
また、自分の意思で学び成長する社員が増えると、チームや社内の士気も向上します。
採用・定着率の向上
副業を容認することで、企業の柔軟性や先進的な姿勢をアピールできます。
特に若い世代は「ワークライフバランス」や「自由な働き方」を重視する傾向にあり、採用競争力の強化に繋がります。



若手人材やクリエイティブ職からの支持が増えるのは企業にとって大きなプラスですね。
また、「副業できる環境」があることで、社員の離職防止にも繋がります。
副業人材活用による企業成長
最近では「副業人材」を企業が積極的に採用するケースも増えています。
本業を持つ人が、勤務時間外に別の会社の仕事をして報酬を得る人材を指します。広義には、企業に属さずフリーランスとして複数の会社と業務委託契約を結ぶ人も含みます。
副業契約をすることで、特定のプロジェクトに必要なスキルを持つ外部人材を短期で雇うことができます。副業人材を採用すると、専門スキルを効率的に導入でき、企業の成長に繋がります。
【企業側】副業デメリット・リスク管理
副業を認めるにあたり、企業側にも一定のリスクがあります。以下の3つは特に意識しておきたいポイントです。
情報漏洩・競業避止の懸念
同業他社での副業は、機密情報の漏洩リスクを伴います。社員が副業を通じて扱う情報の中には、顧客データ・営業ノウハウ・新商品開発・マーケティング戦略・社内システムの構造や内部ルールといった機密情報が含まれます。これらが意図せず副業先に漏れてしまうと、企業の信用失墜や損害賠償問題に発展する可能性があります。
在宅ワークやオンライン業務の増加により、個人PCやクラウド上での情報管理が曖昧になりやすく、情報漏洩のリスクは以前より高まっています。
従業員が自社と競合する事業や企業で働いたり、類似サービスを提供したりすることを禁じるルールです。
競業避止義務の例として、美容サロンスタッフが、個人で同地域にサロンを開業するなどを指します。近隣のお客様を根こそぎ奪われてしまったら、会社の利益を直接脅かす可能性があり、就業規則や雇用契約で明確に禁止されている場合が多いです。



違反した場合、懲戒処分や損害賠償を求められるケースもあります。
労働時間の把握が難しい
副業をしている社員の労働時間をすべて把握するのは難しく、過労による健康リスクも懸念されます。
労働基準法に定める労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間とされていますが、労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で定める範囲内で1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて、労働させることも可能です。
36協定を締結し、届け出ている場合であっても、36協定で定める範囲を超える時間外労働をさせることはできないので、36協定で定める範囲外の時間外労働を可能とするには新たに36協定を締結し直し、届け出ることが必要です。ただし、36協定で延長できる労働時間の限度については、大臣告示(限度基準告示)が定められており、36協定の内容は、限度基準告示に適合したものとするようにしなければならないとされています。(厚生労働省労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)についてより引用)
評価制度・昇進とのバランス
社員の副業について、多くの企業が頭を悩ませているのが“評価の公平性”です。『副業を行う社員』と『副業を行っていない社員』との間で、いかに公平な評価を保つかが課題となっています。
例えば、副業している人が本業のパフォーマンスが一時的に下がった場合や、社内でのチーム活動に参加しづらくなる場合、評価に影響が出ます。一方で、副業によってスキルや視野を広げ、本業で成果を出す社員も増えています。
副業の影響は一概に「良い・悪い」とは言えないため、企業には柔軟かつ成果重視の評価制度が求められています。企業は成果主義や柔軟な評価制度を導入するなど、バランスの取れたマネジメントが必要です。
副業に関する税金の基本と対策
副業を始めるうえで、多くの人が不安を感じるのが「税金」の問題です。
副業を正しく管理することは、トラブル防止だけでなく、長期的に収益を最大化する第一歩です。税金を正しく理解し、賢く運用していきましょう。
確定申告の関連記事


副業収入の税金の仕組み
副業を始めるうえで、多くの人が不安を感じるのが「税金」の問題です。
副業収入は「給与所得」または「雑所得」に分類され、その種類によって税金の扱いが異なります。
どちらの場合も、所得税と住民税の課税対象となります。
副業を始める際は、経費計上や確定申告の方法を理解しておきましょう。
給与所得
副業先と雇用契約を結び、給与として支払われる場合は、給与所得として扱われます。例えば、飲食店やコンビニのアルバイトで得た収入は給与所得に当たります。
アルバイトで得た収入は源泉徴収が行われ、毎月の給与から税金が差し引かれます。
雑所得
個人として報酬を得る場合は雑所得に分類されます。例えば、クラウドソーシング・フリーランス業務・ハンドメイド販売です。
個人として収入を得た場合、収入から経費を差し引いた金額が課税対象です。経費には、通信費・書籍代・作業用パソコンなど、業務に必要な支出を計上できます。
これから副業を始める人におすすめのジャンル
副業を始める際は、「自分の強み × 継続しやすさ × 将来性」の3つを意識すると成功しやすくなります。
ここでは、初心者でも始めやすく、人気の高い4つのジャンルを紹介します。
Webライティング
Webライティングは、パソコン1台で始められる最も始めやすい在宅副業のひとつです。
クラウドソーシングサイト(例:クラウドワークス)を利用すれば、未経験からでも案件を受注可能です。
最初はブログ記事や商品紹介文などの簡単な執筆からスタートし、経験を積むことで専門分野の記事執筆へステップアップできます。
続けるうちに文章力・構成力・リサーチ力が自然と身につくため、本業の報告書やプレゼン資料作成にも役立つスキルになります。
Webライティングスキルを高めれば、1文字1円〜3円以上の高単価案件も目指せるため、スキルアップと収入アップを両立できる副業です。
動画編集


近年のYouTubeやTikTokの需要拡大により、動画編集の副業は人気が上がっています。
「Premiere Pro」や「CapCut」などのソフトを使いこなせるようになれば、クリエイターや企業から継続案件を受けることも可能です。
動画編集は技術職の要素が強いため、努力がそのまま単価に反映されやすい点も魅力です。また、リモートで完結する仕事が多いため、地方在住でも全国・海外のクライアントと繋がれるのも大きなメリットです。



クリエイティブな仕事に興味がある方には特におすすめです。
オンライン講師
自分の得意分野を活かして講師になる副業も注目を集めています。
英会話・プログラミング・ヨガ・イラストなど、スキルや経験をレッスン形式で提供できるのが魅力です。
最近では「ココナラ」など、オンライン講座を開設できるプラットフォームも整備されています。
1回あたり数千円〜数万円の講座収益が見込め、自分の専門知識を資産化できる点も特徴です。
また、人に教えることで自分の知識を整理できるため、自己成長にも繋がります。
EC販売・ハンドメイド


自分のアイデアや作品を販売するEC・ハンドメイド副業は、趣味をそのまま収益化できるのが魅力です。
「minne」などを使えば、誰でも簡単にオンラインショップを開設できます。
アクセサリー・雑貨・イラスト・ハンドメイド服など、個性を活かした一点物は根強い人気があります。
在庫リスクを抑えるために、受注生産やデジタルコンテンツ(例:テンプレート販売・LINEスタンプなど)から始めるのもおすすめです。
副業は「メリットだらけ」だが、正しく理解して取り組むことが大切


副業は労働者だけでなく、企業側にもメリットがあります。ですが、労働者は時間管理と税金対策を意識し、企業はルール整備とリスク管理に注意して副業を行うのが大切です。



副業は、自分の人生を豊かにするチャンスです!ぜひ自分らしい働き方を見つけて、未来に備えましょう。











